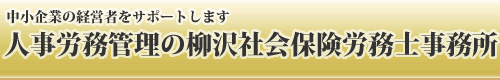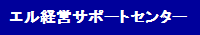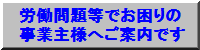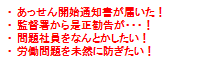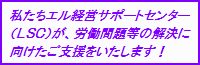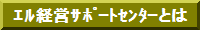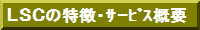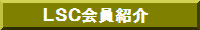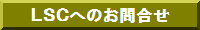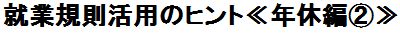
 計画的付与制度の活用
計画的付与制度の活用
従業員の年休請求に対して抵抗感のある経営者は少なくないと思いますが、年休は従業員の英気を養わせ、仕事で高いパフォーマンスを発揮する動機づけとなります。
また、若者や女性を中心に職場に求める価値は変化、多様化しており、自分の時間が持てる職場を魅力と考える傾向にありますので、休暇の取得し易い職場の環境づくりは優秀な人材の獲得や定着に繋がるものと考えられます。
企業にとってトータル的な費用対効果が期待できるよう、経営者には、柔軟な発想と年休制度の上手な活用が求められるところです。
さて、『経営者のための就業規則活用のヒント《年次有給休暇編①》』でご紹介したとおり、使用者は従業員の年休請求を拒否することはできませんが、「計画的付与」という制度を活用すれば、従業員の請求によらず、年休を効果的に消化してもらうことが可能です。 計画的付与とは、労使協定を締結して年休付与の時季に関する定めをした場合には、従業員が保有する年休のうち5日を超える部分について、年休の付与時季を指定することができるという制度です。
例えば、年末年始やお盆などの時季に、一斉または交替で休業させることが可能な企業の場合、計画的付与を活用すれば、事業活動への影響を殆ど被ることなく、従業員の年休取得の促進が実現できますので、労使双方にとってメリットを享受することができます。
なお、計画的付与の注意点としては、年休を指定した日に出勤させる必要が生じたとしても、使用者の時季変更権の行使が認めらないこと(S63.3.14基発150号)や、年休の残日数が計画的付与の休暇日数に満たない従業員に対する取り扱い(通常は、休業手当相当額の支給または特別有給休暇の付与といった対応が行われます。)などが考えられます。
計画的付与を活用するに当たっては、具体的な内容を労使協定に別途定めるとともに、就業規則にはあらかじめ計画的に休暇を指定することがある旨を規定しておきましょう。
 年休一斉付与による年休管理の効率化
年休一斉付与による年休管理の効率化
年休は、従業員が6か月間(翌年度以降は1年間)継続勤務して出勤率80%であれば、従業員の権利として自動的に発生しますので、権利の発生時期はヒトによってバラバラです。 企業としては、入社日の6か月後、1年後(以降、1年毎)に年休を付与すれば法令上問題はありませんが、各従業員の入社日や従業員の数に比例して、年休の管理は大変煩雑な作業となります。
そこで多くの企業では、年休を付与する基準日を一律に定めて年休管理の効率化を図っています(「年休の一斉付与」といいます)。 例えば、毎年4月1日とか事業年度の初日を基準日に設定して、当該基準日に従業員全員の年休一斉に付与すれば、従業員ごとに年休の発生時期を把握する必要がなくなるわけです。
ただし、年休の権利は法律要件に該当したときに自動的に発生するものですから、法定より不利益な取り扱い(例えば、基準日を法定の年休発生日以降に設定するなど)をすることはできません。
年休の一斉付与の要件として、①法定の基準日より前倒しで付与する場合の出勤率の算定に当たっては、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと、 ②翌年度以降の付与日についても、初年度に前倒しした期間以上に繰り上げること、などがあります。
つまり年休の一斉付与を行うに当たっては、使用者は「年休管理の効率化」と引き換えに「従業員の優遇措置」を受け入れることになりますが、従業員が相当数になればいずれ一斉付与の利用を検討するときが来るでしょう。
なお、法定により発生する年休の一部のみを前倒しで付与(例えば、「6か月後に発生する年休の内、5日を入社日に付与する場合」など)する「分割付与」についても上記と同様です。
年休の一斉付与または分割付与を利用する場合は、あらかじめ基準日や付与日数等を設定して、就業規則に定めておきましょう。
 年休の買上げは違法なのか
年休の買上げは違法なのか
従業員は使用者に対し、年度内に行使しなかった年休を賃金として請求することはできませんし、使用者はこれに応じる義務はありません。
また、当該年休分について賃金を支払うこと(いわゆる「年休の買上げ」)をあらかじめ約束して、結果として休暇を与えないことは、労働基準法第39条の年休の趣旨に反して違法と考えられています(S30.11.30基発4718号)。
よって、年休買上げの予約や就業規則に定める買上げ規定を根拠に賃金を支払うこと(結果として、年休取得の妨げとなる行為)は許されません。
但し、上記は法定の休暇日数に関する規制であって、法定の休暇日数を超えた部分の休暇を買上げることは何ら差支えありません。
なお、退職時にまとめて年休を請求して退職日まで出社しない従業員に対し、経営者から「年休の請求を回避する方法はないか」といったご相談を受けることがあります。
残念ながら本ケースでは、使用者は年休の拒否はおろか、時季変更権を行使することもできないため、当該年休の請求を認めざるを得ません(※¹)。
しかし、退職時に限っては、年休取得に係る賃金を支払って出社に応じてもらったとしても、違法ではないと考えられています。これは退職に伴い使用者の時季変更権の行使が不能であることから、いわゆる「買上げ」には該当しないため許されると解されているためです。
ですから、退職までの一定の期間について、引き継ぎ業務等が残っている場合には、出社の見返りに年休の買上げを提案するといった対応は可能と考えられます。
但し、上述の通り、退職が確定する前から、あらかじめ年休の買上げを約束することは、年休の趣旨に反する可能性があるので注意しましょう。
ところで、従業員の年休請求が避けられないことは致し方がないとしても、引き継ぎ業務等が残っているにもかかわらず、必要な業務を履行せずに退職日まですべて年休を取得しまうということであれば、その従業員の誠実性や責任性が疑われるところです。
これはその従業員だけの問題ではなく、企業および上司の教育・指導の在り方、労使間の信頼関係などが影響していることも考えられます。もしそうなのであれば、悪しき慣習が職場に根付く前に、必要な措置を講じることも必要でしょう。
企業にとって常識や良識を持ち合せた人材を育てることは、重要な使命です。 少なくとも従業員が自主的に引き継ぎ業務を行い、また余裕を以て退職の申し出を行うことが当たり前である職場であってほしいものです。
(※¹) 例外的な判例として、退職願提出後の一定期間の勤務を定めた労働組合との覚書を根拠に、時季指定権の行使の制約を認めたものがあります。(大宝タクシー事件 S57.01.29 大阪地裁)
就業規則の作成、変更に関するご相談・お問い合わせはこちらから
文書作成日:2011/06/06
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。